お中元やお歳暮は、感謝の気持ちをかたちにして伝える日本ならではの贈答文化です。ところが、「お中元 お歳暮 総称 何を送る」と検索してしまうように、これらの行事を一括りにした言い方や、実際に何を送ればよいのか迷ってしまう方も少なくありません。そもそもお中元とお歳暮にはそれぞれ意味や贈る時期の違いがあり、適切な品物を選ぶには基本的な知識が必要です。
この記事では、「お中元には何を送るのが良いか」や「お歳暮にはどんなものが喜ばれるのか」といった疑問に答えつつ、贈る相手やシーンに応じた選び方も紹介します。さらに、実際にもらって嬉しいと評判の高いギフトを参考にできるよう、人気ランキングの情報も取り入れました。初めて贈る方はもちろん、毎年の贈り物に変化をつけたい方にも役立つ内容を網羅しています。
- お中元とお歳暮の意味や違いを理解できる
- 「盆歳暮」という総称の意味と使い方を知ることができる
- 贈る相手やタイミングの基準がわかる
- 何を送るべきか人気ギフトや選び方がわかる
お中元お歳暮の総称:何を送れば良いか解説
- 盆歳暮とはどんな意味の言葉か
- 盆歳暮 読み方と使い方の注意点
- お中元とは?意味と時期をおさらい
- お歳暮とは?目的と贈るタイミング
- お中元 お歳暮 違いを分かりやすく比較
- お中元お歳暮の総称:何を送るか迷った時に
盆歳暮とはどんな意味の言葉か

「盆歳暮(ぼんせいぼ)」という言葉には、お中元とお歳暮の2つの贈答習慣をまとめた意味が含まれています。つまり、夏のお中元と冬のお歳暮を総称して「盆歳暮」と呼ぶことで、1年を通じてお世話になった方へ感謝の気持ちを届ける文化を象徴しているのです。
このように言うと少し堅苦しく感じるかもしれませんが、日常的にはあまり使われない言葉です。文献やマナー本、あるいはビジネスマナーの講習などで目にする程度で、一般の会話では「お中元・お歳暮」と個別に表現されることが多いでしょう。
言ってしまえば、「盆歳暮」という言葉は、日本人の人間関係における気遣いや礼節をまとめて表現した語句でもあります。贈り物の内容やタイミングに気を配ること自体が、相手への思いやりを形にする行動なのです。ビジネス上のお付き合いでも家庭内でも、「贈る気持ち」を大切にすることが信頼関係を育む要素となっています。
ただし、注意したいのは「盆歳暮」という言葉そのものが口語では使われにくいという点です。メールや手紙に用いる場合でも、文脈によっては「お中元・お歳暮」と具体的に記す方が誤解を避けられます。したがって、使う場面には慎重さが求められます。
このように「盆歳暮」は、単なる贈答行為ではなく、年中行事の中で人と人とのつながりを見直す機会でもあると言えるでしょう。
盆歳暮 読み方と使い方の注意点

「盆歳暮」は「ぼんせいぼ」と読みます。漢字だけを見ると読み方に迷いやすいため、初めて目にした方は戸惑うかもしれません。この言葉は、贈答文化を表す一種の総称として使われていますが、日常的な言葉ではなく、やや硬い印象を持つ表現です。
例えば、ビジネスマナーを教える研修や、礼儀作法に関する書籍、または冠婚葬祭関連の文章の中で見かけることがあります。しかし、日常会話や手紙文で使う場合には注意が必要です。なぜなら、「盆歳暮」という語が広く知られていないため、受け取る相手に意味が正確に伝わらない可能性があるからです。
こう考えると、「お中元とお歳暮」など具体的に説明した言い回しの方が、相手にとって親切です。とくに社外文書や目上の方への表現では、あえて難しい熟語を避けることで、より丁寧な印象を与えることができます。
また、「盆歳暮」は一般に口語ではほとんど使われないため、会話中にこの言葉を用いると相手が理解しにくい場合もあります。そのため、使用するシーンは限定的にとどめておいた方がよいでしょう。
このように、「盆歳暮」という語を使用する際には、相手や場面に配慮しながら使うことが大切です。あえて難しい言葉を使うのではなく、わかりやすい表現を選ぶことが、マナーを伝える上でもっとも効果的です。
お中元とは?意味と時期をおさらい

お中元とは、夏の時期に日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝えるために贈り物をする日本の伝統的な習慣です。主に上司や取引先、親戚など、目上の方に向けて贈られることが多く、礼儀を重んじる日本文化の一端を担っています。
起源をたどると、お中元は中国の道教における「中元」という日が元になっており、日本ではこれが「お盆」の風習と結びついた結果、夏に贈り物をする行事として定着しました。つまり、お中元には季節の挨拶だけでなく、健康や長寿を願う意味も込められているのです。
贈る時期については、地域によって多少異なります。関東では7月初旬から15日までが一般的ですが、関西では7月中旬から8月15日ごろまでが目安となっています。したがって、相手の住んでいる地域に合わせて送る時期を調整することが重要です。
ただし、時期を過ぎてしまった場合には「暑中御見舞」や「残暑御見舞」と表書きを変えて贈るのがマナーです。これは遅れてしまったことに対する配慮であり、相手への敬意を忘れない日本らしい慣習といえます。
お中元で選ばれる品物には、ビールやジュース、ゼリー、冷たいお菓子、商品券など、夏の暑さを乗り切るのにぴったりのものが多く含まれます。ただし、あまり高価すぎる品物はかえって相手に気を使わせるため、3,000円〜5,000円程度が相場となっています。
このように、お中元は単なる贈答ではなく、季節の節目に感謝の気持ちをかたちにして伝える日本独自の文化です。品物選びやタイミング、金額にも配慮しながら、相手に喜ばれる贈り方を心がけたいところです。
お歳暮とは?目的と贈るタイミング

お歳暮とは、1年の終わりにお世話になった方へ感謝の気持ちを込めて贈り物を届ける、日本の伝統的な習慣です。年末のご挨拶として位置づけられており、日頃から支えてくれた人たちに「今年もありがとうございました」という気持ちを示す行為といえます。
起源をたどると、お歳暮はもともと先祖へのお供え物を年末に届ける風習に由来しています。それが時代とともに家族や親戚、さらに仕事上の関係者などへ広がり、現在のような贈答文化に発展しました。こうした背景からもわかるように、お歳暮は単なる形式的な贈り物ではなく、人間関係を円滑に保つための大切な行動とされています。
贈る時期は地域によって若干の違いがありますが、一般的には12月初旬から12月20日ごろまでが適当とされています。特に関西地方では、12月13日の「事始め」以降に贈る習慣が残っています。ただし、年末ぎりぎりになると相手側も慌ただしくなるため、余裕をもって早めに贈るほうが好印象を与えるでしょう。
なお、何らかの事情で年内に贈れなかった場合は、表書きを「御年賀」や「寒中御見舞」に変えて、年明けに贈ることも可能です。このときは、1月7日(松の内)までを「御年賀」、それ以降は「寒中御見舞」とするのがマナーとされています。
お歳暮で人気の品物には、年末年始の団らんで役立つ食材や飲み物が多く選ばれます。たとえば、ハムや肉の詰め合わせ、高級なお菓子、縁起の良い海産物などが挙げられます。また、お中元よりやや高めの金額(5,000円前後)が一般的とされ、相手との関係性によって調整するのが良いでしょう。
このように、お歳暮は1年間の感謝を形にして伝える大切な機会です。時期や贈る品物の選び方に配慮しながら、相手に失礼のないよう丁寧な対応を心がけましょう。
お中元 お歳暮 違いを分かりやすく比較

お中元とお歳暮は、どちらもお世話になった方への感謝を伝える贈り物ですが、その意味やタイミング、マナーには明確な違いがあります。この違いをしっかり理解しておくことは、適切な贈答を行ううえでとても重要です。
まず、最も分かりやすい違いは贈る時期です。お中元は夏(7月〜8月)、お歳暮は年末(12月)に贈ります。お中元は上半期のお礼、お歳暮は1年間の締めくくりとしての感謝を表すタイミングです。地域によっても差があり、例えば関東ではお中元を7月上旬に贈る一方で、関西では8月15日頃までが目安となります。お歳暮も同様に、12月13日から20日頃までが一般的とされています。
次に、贈る品物の内容や価格帯にも違いがあります。お中元は夏に贈るため、ゼリーやジュース、冷たいスイーツなど涼を感じる品が好まれます。一方、お歳暮では年末年始に役立つ肉や魚介類、ハムセット、アルコール類などが人気です。また、金額に関しては、お中元が3,000円〜5,000円程度に対して、お歳暮はやや高めの5,000円前後が相場とされています。

さらに、表書きや熨斗(のし)の使い方にも違いがあります。お中元の表書きは「御中元」と書きますが、時期を過ぎた場合は「暑中御見舞」や「残暑御見舞」に変更します。一方でお歳暮は「御歳暮」と書き、年末に間に合わなければ「御年賀」や「寒中御見舞」として贈るのがマナーです。こうした形式面にも注意を払うことが、失礼のない贈答に繋がります。
最後に、心理的な違いにも触れておきましょう。お中元は比較的カジュアルな印象があり、「日頃のお礼」として気軽に贈る傾向があります。それに対してお歳暮は「1年の締めくくり」という位置付けが強く、より丁寧さや正式な意味合いが求められます。そのため、どちらか一方しか贈らない場合は、お歳暮を選ぶ方がフォーマルで失礼が少ないと考えられています。
このように、時期・意味・贈る内容・マナーのすべてにおいて、お中元とお歳暮は異なる要素を持っています。それぞれの違いを理解し、適切な贈り方を心がけることで、相手に対する感謝の気持ちがより一層伝わるでしょう。
お中元お歳暮の総称:何を送るか迷った時に
- お中元お歳暮は誰に送るべきかの基準
- お歳暮は何がいい?人気アイテムを紹介
- お中元おしゃれな贈り物の選び方
- 年配の方におすすめのお中元ギフト
- もらって嬉しい ランキングから選ぶ
- 本当に喜ばれる贈り物とは?
- 地元のギフトという選択肢もおすすめ
お中元お歳暮は誰に送るべきかの基準

お中元やお歳暮は、誰に送るべきかを迷いやすい贈り物です。明確なルールがあるわけではありませんが、基本的な考え方としては「日頃お世話になっている方」に対して感謝の気持ちを表すことが目的です。したがって、仕事関係・親族・友人など、関係性に応じて判断することが大切です。
まず、仕事関係での贈答はよく見られるケースです。たとえば、取引先の担当者や、会社の上司、過去に指導を受けた恩人などに送ることが一般的です。ただし、最近では社内での贈答を禁止している企業もあるため、社内規定や社風には十分に注意しましょう。とくに公務員や政治家など、一部の職業では贈答が制限されている場合もあります。
家庭内では、両親・義理の両親・親戚といった家族関係の方々に送ることが多く見られます。中でも、結婚を機に義理の家族と新たな関係を築いた場合、お中元やお歳暮を通して感謝を伝える機会になります。付き合いの深さや親しさを考慮しながら、毎年継続的に贈るようにすると良好な関係の維持にもつながります。
他にも、恩師や習い事の先生、地域の世話役、長年の友人に対して贈る方も少なくありません。形式にとらわれすぎず、「ありがとうを伝えたい相手」を基準にするのが最も自然です。
ただし、一度贈り始めた場合には毎年継続することが望ましいとされています。思いつきで贈って翌年からやめてしまうと、かえって失礼な印象を与えてしまう恐れがあります。そのため、贈るかどうか迷ったときは、長く付き合いたい相手かどうかを考えて判断するとよいでしょう。
このように、お中元やお歳暮は「形式よりも気持ち」を優先しつつ、相手との関係性やマナーを考慮して贈る相手を決めるのがポイントです。
お歳暮は何がいい?人気アイテムを紹介
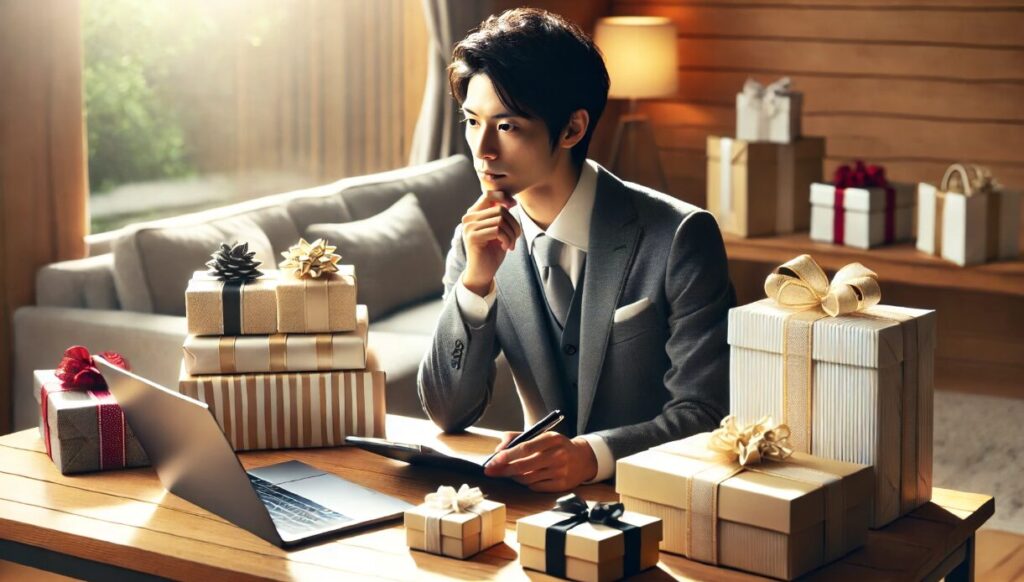
お歳暮で何を贈るべきか悩んだときは、相手の家族構成や年齢、嗜好を参考にしながら選ぶことが大切です。年末年始の団らんや冬のごちそうに活用できる品が人気で、実用性が高く、かつ華やかさのある商品が選ばれる傾向にあります。
まず定番として挙げられるのは「ハムやソーセージの詰め合わせ」です。保存が利き、年末年始の食卓でも重宝されるため、毎年安定した人気を誇ります。また、「高級牛肉」や「カニ・いくら・数の子」などの海産物も、特別感があるギフトとして高評価です。こうした商品は親族が集まる家庭にとって、特別なごちそうとして喜ばれることが多いです。
さらに、「お菓子の詰め合わせ」や「フルーツギフト」も人気です。特に小さなお子さんがいる家庭や甘いものが好きな方には、洋菓子や和菓子のギフトセットが好まれます。ジュースやコーヒー、紅茶のセットなど飲料系のギフトも日常使いしやすく、相手を選ばず贈りやすい品です。
一方で、「カタログギフト」も選択肢として注目されています。相手に好きなものを選んでもらえるため、好みが分からない場合でも安心して贈ることができます。見た目もスマートで、価格帯も幅広く選べるため、法人向けや遠方の相手にも便利です。
ただし、目上の方への贈り物としては注意が必要な品もあります。たとえば、刃物(縁を切る)、履物(踏みつける)、肌着(施しと受け取られる)などは避けるべきとされています。また、あまりに高額なものを贈ると、相手に気を遣わせる結果となることもあるため、相場(3,000円〜5,000円)を意識することが大切です。
このように、お歳暮には「使いやすく、喜ばれるもの」を贈ることがポイントです。相手のライフスタイルを想像しながら、心のこもった選び方を心がけましょう。
お中元おしゃれな贈り物の選び方

お中元で贈る品物に「おしゃれさ」を求める方が増えています。従来の形式的なギフトに加え、センスが感じられる贈り物を選ぶことで、相手に一層の印象を与えることができるからです。ここでは、おしゃれなお中元を選ぶための具体的な視点をご紹介します。
まず注目されているのは「見た目が美しい商品」です。たとえば、フルーツゼリーや洋菓子セットは、パッケージに高級感があり、冷蔵庫に並べても絵になるようなデザイン性の高いものが人気です。さらに、最近ではSNS映えを意識したカラフルなスイーツや、木箱に入った高級感のある和菓子なども喜ばれています。
次に「ブランド性のある商品」もおしゃれギフトとして選ばれやすい傾向があります。老舗の茶舗や有名なスイーツブランドから出ている夏限定ギフトは、品質の信頼性があるだけでなく、「選び抜いた感」が伝わるため、受け取る側にも好印象を与えます。特に、ブランドを意識する方や目上の方には効果的なアプローチといえるでしょう。
他には、「環境や健康に配慮された商品」も最近では人気があります。例えば、無添加のフルーツジュース、オーガニック素材のスイーツなどは、小さなお子さんや健康を気にするご家庭にも贈りやすいアイテムです。ギフト選びの段階で「相手の暮らしに寄り添う」という視点を持つことで、より洗練された印象を残すことができます。
もちろん、おしゃれさを追求しすぎると使いにくいものや実用性の低いものを選んでしまうリスクもあるため注意が必要です。見た目だけで選ぶのではなく、「相手が本当に喜んで使えるかどうか」を念頭に置くことが大切です。
こうして考えると、おしゃれなお中元とは「デザイン性と実用性のバランスが取れているギフト」だと言えます。感謝の気持ちを込めて、センスよく、そして思いやりのある贈り物を選ぶことが、好印象につながるポイントです。
年配の方におすすめのお中元ギフト

年配の方へお中元を贈る際には、若い世代とは異なる視点での選び方が求められます。量より質を重視し、食生活やライフスタイルに無理なくフィットする贈り物を選ぶことが、相手への配慮として重要になります。
多くの場合、60代以上の方々は食が細くなっていたり、健康を気にしている傾向があるため、大容量の食品や高カロリーな商品は避けたほうが無難です。その代わりに、上質で少量、かつ日持ちのするギフトが喜ばれます。たとえば、個包装された和菓子や洋菓子、無添加のフルーツジュース、高級煎茶や抹茶などは、年配の方から高い評価を得やすいアイテムです。
また、調理の手間がかからない惣菜セットや、電子レンジで温めるだけで食べられる焼き魚の詰め合わせなども人気があります。忙しい日や体調が優れないときにも負担にならず、日々の生活に役立つギフトとして重宝されます。さらに、素麺やうどんといった乾麺のセットは、夏の暑さで食欲が落ちる季節にも食べやすく、毎年安定した人気を誇っています。
このとき注意したいのは、相手の好みに偏りすぎないことです。お酒を控えている方にお酒のセットを贈る、甘いものが苦手な方に洋菓子を贈るといったミスマッチは避けるべきです。可能であれば、事前に本人やご家族に好みを確認しておくと安心です。

また、見た目の美しさや上品な包装も年配の方には喜ばれるポイントです。老舗の和菓子店や地域特産品を扱うブランドの品物は、贈り手のセンスや気遣いが伝わりやすく、印象にも残りやすいでしょう。
このように、年配の方に贈るお中元は「食べやすさ」「健康への配慮」「見た目の上質さ」を意識して選ぶと失敗しにくくなります。形式にとらわれることなく、相手に本当に喜ばれるギフトを選ぶ姿勢が最も大切です。
もらって嬉しい ランキングから選ぶ

お中元やお歳暮を選ぶ際に、「何を贈れば喜ばれるのか」と悩む方は少なくありません。そんなときに参考になるのが、人気アイテムのランキングです。多くの人に選ばれている商品には、贈られて嬉しい理由があり、外れにくい傾向があります。
まず、ランキングの上位に常に登場するのが「アイスクリーム」です。夏の贈り物であるお中元にぴったりの涼を感じられるスイーツで、子どもから大人まで幅広く喜ばれます。特に高級感のある有名ブランドのアイスは特別感があり、受け取った人の記憶にも残りやすい贈り物です。
次に人気が高いのは「チョコレート」や「ゼリー・ムース」などのデザート類です。華やかなパッケージと豊富なバリエーションが魅力で、贈る側のセンスが光るジャンルでもあります。甘いものが好きな方にはもちろん、家族みんなで楽しんでもらえる点でも評価が高いです。
さらに「フルーツ」もランキング上位の常連です。旬のメロンやさくらんぼ、マンゴーなどは贈答用にふさわしい華やかさと高級感があります。一方で、食べきれない量を贈ってしまうと相手の負担になるため、少量で質の高いセットを選ぶのがポイントです。
「カタログギフト」や「商品券」も人気があります。相手に選んでもらえるという利便性があるため、好みがわからない相手やビジネス関係の相手には特に重宝されます。実用的でありながら失礼になりにくいため、幅広いシーンで活用できます。

なお、ランキングで上位にあがる品でも、相手の生活スタイルに合っていない場合は注意が必要です。例えば、一人暮らしの方に大量の商品が届くと負担になることもあります。そのため、贈る前に相手の家族構成や趣味嗜好をさりげなくリサーチしておくことが大切です。
このように、「もらって嬉しいランキング」は選び方のヒントになりますが、あくまで相手に合わせた調整が必要です。人気商品を参考にしつつ、心配りのあるギフト選びを心がけましょう。
本当に喜ばれる贈り物とは?

本当に喜ばれる贈り物とは、受け取った相手が「自分のことを考えて選んでくれた」と感じられるような、心配りが伝わる品です。値段やブランドに関係なく、「相手にとってちょうどよいもの」であることが最大のポイントになります。
贈り物選びでまず大切なのは、相手のライフスタイルや好みを理解することです。たとえば甘いものが好きな方には洋菓子や和菓子、健康に気を使っている方には無添加の食品やノンカフェインの飲み物といったように、生活背景に合ったギフトは自然と喜ばれます。逆に、高級であっても食べきれない量だったり、好みに合わないものだったりすると、かえって相手に気を遣わせてしまうことにもなりかねません。
このとき意識したいのは、「自分が贈りたいもの」ではなく「相手が受け取りやすいもの」を基準にすることです。たとえば一人暮らしの高齢者には、冷蔵保存が不要で日持ちのする個包装の商品が便利ですし、子育て中の家庭には家族で楽しめる飲料やお菓子のセットが適しています。
また、包装やメッセージカードといった“贈り方”にも配慮があると、さらに喜ばれる可能性が高くなります。簡単な一言でも「いつもありがとうございます」「暑い日が続いていますのでご自愛ください」と添えられていれば、品物以上に温かい印象を与えることができます。
なお、あまりに高額な品や目上の人への商品券などは、場合によっては「無遠慮」と捉えられることもあります。形式やマナーにも注意を払いつつ、相手との関係性に合ったものを選ぶことが大切です。
このように、真に喜ばれる贈り物は「モノ」ではなく「気持ち」が伝わるものです。受け取る人の立場になって考えることで、記憶に残る贈り物へと変わっていきます。
地元のギフトという選択肢もおすすめ
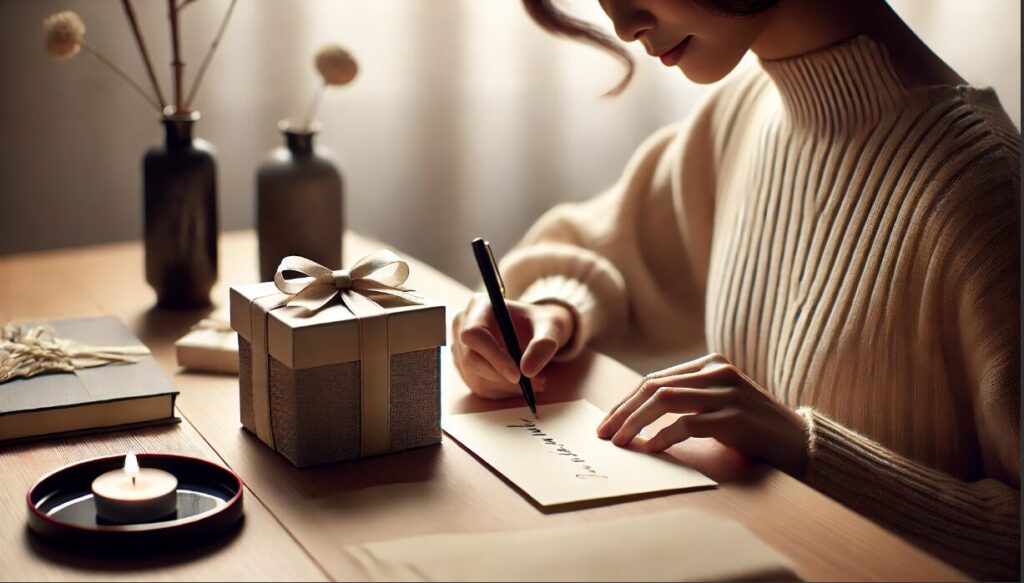
最近注目を集めているのが、「地元のギフト」という贈り物のスタイルです。これは、贈る人または受け取る人の出身地や思い出のある土地の特産品を選べるカタログギフトで、より個性と温かみのあるプレゼントが実現できるのが特徴です。
このようなギフトの最大の魅力は、「どこにでもあるもの」ではなく、「その地域にしかない魅力的な商品」を贈れることです。たとえば、長野県のりんご、宮城の牛タン、大分のかぼすといったように、地域の食文化や風土を感じられる品々は、ありきたりなギフトとは違った驚きと喜びを与えてくれます。

また、地元のギフトは「カタログ形式」であることが多く、受け取った側が好きなものを選べるという点でも非常に実用的です。好みが分からない相手にも失敗なく贈れるため、ビジネスシーンやフォーマルな贈答にも対応しやすいのが利点です。
さらに、地域の生産者がこだわりを持って作った商品が紹介されている「ストーリーカード」なども付いていることがあり、単なる物のやりとりを超えた“体験型の贈り物”としての価値を感じられる構成になっています。こうしたギフトは、商品を通じてその土地の魅力や生産者の思いが伝わるため、特別感もひとしおです。

注意点としては、季節によって発送時期が異なる商品も多いため、贈るタイミングや内容を事前に確認しておくことが必要です。ただし、それも含めて「旬の味を楽しんでもらう」という贈り方の一部として受け止めれば、むしろ特別な体験として相手の印象に残りやすくなります。
お中元 お歳暮 総称 何を送るか迷った時の基礎まとめ
- 「盆歳暮」はお中元とお歳暮をまとめた総称
- 「盆歳暮」は日常会話では使われにくい表現
- お中元は夏に贈る感謝の習慣
- お歳暮は年末に贈る1年の締めくくりの挨拶
- お中元は地域によって贈る時期が異なる
- お歳暮の贈答タイミングは12月初旬から20日前後
- お中元とお歳暮では品物や金額相場が異なる
- お中元はジュースやゼリーなど涼を感じる品が人気
- お歳暮はハムや海鮮、お菓子など豪華な食品が選ばれる
- 贈る相手は「日頃お世話になっている人」が基本
- ビジネスや家族関係では事前のルール確認が必要
- 形式よりも相手に合った品選びが最も重要
- 高価すぎる品はかえって負担になりやすい
- 年配の方には少量高品質で日持ちする品が好まれる
- 地元のギフトは特別感と実用性を兼ねた新たな選択肢

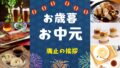
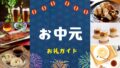
コメント