お歳暮やお中元をいただいた際、感謝の気持ちをきちんと伝えるために「お礼状」を出すのは大切なマナーです。しかし、「何を書けばいいのかわからない」「堅苦しくなりすぎないか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。特に、個人間でのやりとりでは形式ばらず、かつ失礼にならないバランスの取れた表現が求められます。
この記事では、「お歳暮 お中元 お礼状 例文 個人」というテーマで、丁寧ながらも堅苦しくない文例や書き方のポイントをわかりやすく紹介していきます。親戚や友人、職場の方など、相手との関係性に合わせた文面の工夫や、季節感を出すための表現、テンプレートの活用法なども交えて解説します。
初めてお礼状を書く方や、文章に自信がない方でも安心して活用できる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
- お歳暮やお中元のお礼状の出すタイミングや基本マナー
- 個人で使える丁寧かつ堅苦しくない文例の書き方
- 食べ物や果物など品物別のお礼状の具体的表現
- 地元のギフトを活用した感謝の伝え方とそのメリット
お歳暮お中元のお礼状例文:個人向けの基本マナー
- お礼状はいつまでに出すべき?
- 親戚堅苦しくないお礼状の書き方
- 食べ物お礼状文例:個人に合う例とは
- 果物お礼状の例文に使える表現集
- テンプレートを活用した簡単なお礼状作成法
お礼状はいつまでに出すべき?

お中元やお歳暮をいただいた場合、お礼状はなるべく早めに出すことが大切です。
目安としては、品物が届いてから3日以内に出すのが一般的なマナーとされています。もちろん、状況によって多少前後することは問題ありませんが、長く放置してしまうと相手に対して失礼な印象を与えてしまう恐れがあります。
なぜ3日以内が望ましいのかというと、お礼状の本来の目的は「感謝の気持ちを伝える」と同時に「確実に品物を受け取ったことを知らせる」ことにあります。特に贈り手は、届いたかどうか不安に思っている場合も多く、受け取りの報告を含めたお礼は非常に重要な役割を果たします。
例えば、冷蔵が必要な果物や生鮮食品などは日持ちしないため、受け取りの連絡が遅れることで「きちんと届いていないのでは?」と贈り主が不安になってしまいます。そうした心配を避けるためにも、まずは到着当日か翌日に電話やメールなどで受け取りの報告を行い、その後あらためてお礼状を送る流れが理想的です。
ただし、すぐにお礼状を書けない場合もあるでしょう。その場合は、まずは簡単な連絡を入れて感謝の気持ちを伝えておくことで、マナー違反にはなりません。お礼状は、気持ちがこもった丁寧な手紙であるほど相手の印象に残ります。形式だけでなく、タイミングも大切にしましょう。
なお、お礼状が遅れてしまった場合には、お詫びの一言を添えることも忘れないようにします。「ご連絡が遅れまして申し訳ございません」と一言加えるだけでも、相手の受け取り方は大きく変わってくるはずです。
親戚堅苦しくないお礼状の書き方

親戚にお中元やお歳暮をいただいた際、お礼状を書くのはマナーのひとつですが、堅苦しすぎる表現はかえってよそよそしい印象になることもあります。特に普段から気軽に連絡を取り合うような親しい親戚に対しては、形式にこだわりすぎず、気持ちが伝わることを優先するのがポイントです。
ここで大切なのは、「丁寧さ」と「親しみやすさ」のバランスです。ですから、あえてビジネス文書のようなかしこまった言い回しを避け、自然な会話に近い表現を使うことで、感謝の気持ちがより伝わりやすくなります。
例えば、「このたびはお中元をありがとうございました」という硬い表現よりも、「とても素敵なお中元をありがとう。家族みんなで美味しくいただきました」といった柔らかい口調にすることで、より温かい印象になります。
それでもマナーを重んじる場面では、最低限の形式は保つべきです。頭語として「拝啓」や「前略」、結語として「敬具」や「草々」などを適切に使えば、親しみを持たせつつ失礼のないお礼状になります。
また、手紙の形式にこだわりすぎず、はがきやメールを利用するのも一つの手です。特に高齢の親戚には手書きのはがきが喜ばれますし、若い世代であればメールやLINEなどでも失礼にならない場合もあります。
ただし、注意したいのは「略式すぎる表現」です。いくら親しい間柄でも、絵文字やカジュアルすぎる言葉遣いは避けた方が無難です。たとえ文章が短くても、心のこもった言葉で感謝を伝えることを心がけましょう。
こちらの記事もオススメです(^^)/
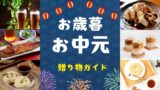
食べ物お礼状文例:個人に合う例とは

食べ物を贈ってくれた相手にお礼状を書く際には、もらった品物への具体的な感想を添えることが、感謝の気持ちをしっかり伝えるポイントになります。特に個人間でのやりとりであれば、形式ばらずに素直な感想を伝える方が好印象です。
言ってしまえば、単に「ありがとうございました」だけでは、どんな品物だったのか、嬉しかったのかどうかが相手に伝わりにくいものです。逆に、「家族みんなで旬の桃をいただき、甘くてとても美味しかったです」や、「立派な和牛をありがとうございました。さっそく焼肉にしていただき、贅沢なひとときを過ごせました」といった具体的な文面にすることで、受け取った側の喜びがしっかり伝わります。
こうした表現には、いくつかのメリットがあります。まず、相手が選んだ品物が喜ばれたことが伝わり、選んだ側としても嬉しくなるものです。また、今後もどのような品を贈ればよいかの参考になることもあります。
一方で注意したい点もあります。それは、「好みに合わなかった場合」の対応です。たとえ自分にとってはあまり嬉しくない内容だったとしても、相手の気遣いには変わりありません。だからこそ、「お気遣いいただきありがとうございました」「ご丁寧なお品をいただき感謝しております」といった表現を使い、品物自体への具体的な言及を避けるという工夫も必要です。
このように考えると、食べ物に対するお礼状は、形式以上に「感想」と「感謝」をどう伝えるかが大切です。自分らしい言葉で、相手の気持ちに丁寧に応えるよう心がけましょう。
こちらの記事もオススメです(^^)/
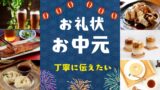
果物お礼状の例文に使える表現集

果物をいただいた際のお礼状には、品物の種類に応じた表現や、季節感のある言葉を取り入れることで、より気持ちのこもった文章になります。特に果物は季節性が高く、味や香りに対する感想が書きやすいため、具体的に「どう感じたか」「誰と楽しんだか」などを添えるのが効果的です。
例えば、夏に桃やスイカをいただいた場合は、「冷やして家族でいただきました。みずみずしく甘さも格別で、暑さを忘れるような美味しさでした」という表現が自然です。ぶどうであれば、「粒が大きくて、口に入れた瞬間に広がる香りに癒やされました」のように、味覚と香りの両面を言葉にするのも良いでしょう。
また、贈ってくれた相手への配慮も忘れてはいけません。例えば「お心のこもった贈り物、誠にありがとうございました」といった丁寧な一文を冒頭または締めに添えることで、形式としての礼儀も整います。これにより、堅苦しくなりすぎずに、かつ礼を尽くした印象を残せます。
このとき使えるフレーズとしては、以下のような表現があります。
- 「このたびは季節の果物をお贈りいただき、心より御礼申し上げます」
- 「早速冷やしていただき、家族皆で美味しく味わいました」
- 「自然の甘さが口いっぱいに広がり、とても幸せな気持ちになりました」
- 「お気遣いをいただき、大変ありがたく存じます」
- 「皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます」
ただし注意したいのは、事実と異なることを書くのは避けるべきという点です。例えばアレルギーなどで果物を食べられなかった場合、「ありがたく頂戴いたしました」といった表現にとどめるのが無難です。
果物のお礼状は、相手の選んだ贈り物に対する「感謝」と「具体的な感想」を伝える絶好の機会です。形式ばかりにとらわれず、素直な気持ちを丁寧に言葉にするよう心がけましょう。
テンプレートを活用した簡単なお礼状作成法

お中元やお歳暮のお礼状を書くとき、「何を書けばいいかわからない」「言葉が思い浮かばない」と感じる方は少なくありません。そんなときに便利なのが、テンプレートを活用する方法です。基本的な構成と例文が整っていれば、書く側の心理的負担も軽減され、効率よく感謝の気持ちを伝えることができます。
テンプレートを使う最大のメリットは、文章の型がすでに決まっているため、書き慣れていない人でも失礼なく、まとまりのある手紙が作れる点です。特に初めてお礼状を書く人や、短時間で複数通を書かなければならない場合には有効な方法といえるでしょう。
お礼状の基本的な構成は、以下のようになります。
- 頭語(例:「拝啓」「前略」など)
- 時候の挨拶と相手の安否を尋ねる言葉
- 感謝の言葉(お中元・お歳暮をいただいたことへのお礼)
- 品物に関する感想や使い道などの具体的内容
- 相手の健康を気遣う言葉
- 結語(例:「敬具」「草々」など)
- 差出人の名前と日付
例えばビジネスシーンで使えるテンプレートは以下のような形です。
拝啓 盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、このたびはご丁寧なお中元の品を賜り、誠にありがとうございました。
早速、社員一同で美味しく頂戴し、暑い夏に元気をいただいております。
今後とも変わらぬお付き合いを賜りますようお願い申し上げます。
末筆ながら、皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。
敬具
一方、親しい相手に送る場合には、もう少しくだけた文面も可能です。
前略 暑さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。
このたびは、美味しい果物をお送りいただきありがとうございました。
家族みんなでおいしくいただき、楽しいひとときを過ごせました。
くれぐれも体調に気をつけて、素敵な夏をお過ごしください。
草々
注意点としては、テンプレートを「そのまま使う」だけでは気持ちが伝わりづらくなる可能性もあるということです。相手との関係性や受け取った品物に応じて、文面の一部を適切にアレンジすることが大切です。特に相手の名前や贈られた品の内容を具体的に書き加えることで、より温かみのある手紙になります。
このように、テンプレートはお礼状作成の強力な味方になりますが、ほんの少しだけ自分らしい言葉を添えることで、相手にとっても印象的な一通になるでしょう。
お歳暮お中元のお礼状例文:個人におすすめ文例集
- お歳暮お礼状例文:個人で使える定番表現
- 時候の挨拶を取り入れた季節感の出し方
- 親しい間柄でも失礼にならない文例
- ビジネスメールでも使えるお礼の表現
- 地元のギフトで感謝を形にする方法
- カジュアルなお礼状にも使える文例集
- 地元のギフトの特徴とおすすめポイント
お歳暮お礼状例文:個人で使える定番表現

お歳暮のお礼状は、個人で書く場合でも最低限の礼儀をおさえながら、感謝の気持ちを相手に伝えるための表現を選ぶことが大切です。文章が堅くなりすぎず、かといってカジュアルすぎない、バランスの取れた言葉遣いが理想的です。
ここでは、誰にでも使いやすく、失礼のない定番表現を紹介します。まず冒頭の書き出しには、相手の健康や近況を気遣う文章が基本になります。例えば、「寒さ厳しき折、お変わりなくお過ごしでしょうか」「年末を迎え、お忙しくされていることと存じます」といった文が自然です。
続いて、贈り物に対する感謝を伝える際には、「このたびは結構なお品を頂戴し、誠にありがとうございました」や「ご丁寧なお歳暮の品、ありがたく拝受いたしました」などが一般的です。ポイントは、受け取ったことをしっかり伝えつつ、相手の心遣いに対して感謝を表現することです。
また、締めくくりの部分では、相手の健康を願う言葉を入れることで丁寧な印象になります。「年末に向け、くれぐれもご自愛くださいませ」「寒さ厳しき折、お体を大切にお過ごしください」といった表現は、季節感とともに相手への思いやりが伝わります。
これらの定番表現は、文面のテンプレートとしても活用できますが、大切なのはあなた自身の言葉として自然に組み立てることです。決まり文句をそのまま並べるのではなく、相手との関係性を意識しながら、少しだけアレンジを加えると、より心のこもったお礼状になります。
時候の挨拶を取り入れた季節感の出し方

時候の挨拶は、季節の移り変わりを感じさせる表現を取り入れた冒頭の挨拶文であり、お歳暮やお中元のお礼状などの手紙において重要な役割を果たします。これにより、文章に自然な流れと温かみを与えることができます。
例えば、12月のお歳暮のお礼状であれば、「師走の候」「歳末の折」「寒気厳しき折」といった表現が時期にふさわしい挨拶になります。それに続けて、「皆様にはお健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます」「お風邪など召されていませんでしょうか」などと続けると、形式にのっとりながらも思いやりのある文章に仕上がります。
一方、時候の挨拶は決して堅苦しいものばかりではありません。親しい相手であれば、「今年も残りわずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか」といった、やわらかい口調での導入も好まれます。書き出しに季節感を織り交ぜることで、自然な会話のような文章になり、手紙全体が読みやすくなります。
時候の挨拶を選ぶ際は、送る時期に適した言葉を選ぶことがポイントです。例えば、11月下旬であれば「晩秋の候」、12月上旬は「師走の候」、年末に近づくにつれて「寒冷の折」「歳末の候」などに変化していきます。
注意点としては、あまりに形式的すぎる挨拶ばかり並べると、文章がよそよそしく感じられることです。形式は大切ですが、相手との距離感に合わせて柔らかさを加えることも忘れないようにしましょう。
このように、時候の挨拶を上手に取り入れることで、手紙全体が季節感にあふれ、読み手にとっても印象深い内容になります。特にお歳暮やお中元のような季節の贈り物に対するお礼状では、時候の挨拶が文章の格を決める要素にもなるのです。
親しい間柄でも失礼にならない文例
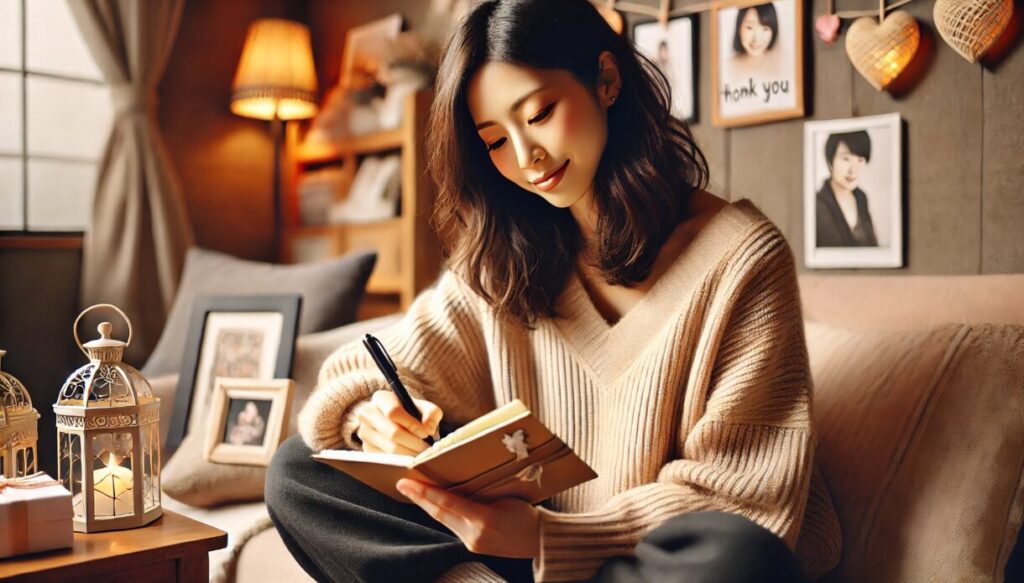
親しい間柄においても、お中元やお歳暮を受け取った際には、丁寧なお礼を伝えることが礼儀です。ただし、形式張った言葉ばかりではかえって距離を感じさせてしまうこともあるため、親しみを感じさせつつ、礼儀をわきまえた表現が求められます。
例えば、親しい友人や親戚に対するお礼状の文面では、「このたびは美味しいハムの詰め合わせをありがとうございました」といった、素直で率直な表現が効果的です。さらに、「おかげさまで、家族みんなで楽しい食卓を囲むことができました」など、贈り物がどのように役立ったかを伝えることで、感謝の気持ちがより具体的に伝わります。
また、かしこまりすぎず、それでいて失礼にならない一文として、「いつもながらのお心遣いに感謝いたします」や「季節のご挨拶、ありがたく頂戴しました」などの表現もよく使われます。これにより、相手に対して敬意を払いつつも、程よい距離感を保つことができます。
結語も、硬すぎない表現を選ぶと良いでしょう。例えば、「草々」「それでは、寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください」といった文で締めると、形式的でない温かみのある終わり方になります。
ただし、親しさを理由にして過度に砕けた言葉を使うのは避けましょう。絵文字や口語表現、「マジでありがとう」といった言い回しは、たとえ関係が深くても書面では適切とは言えません。手紙には書き手の人柄が出るため、親しい相手にこそ、丁寧な気遣いをもって接することが大切です。
このように、親しい相手に送るお礼状も、基本的なマナーを守りながら、気持ちの伝わる言葉選びを意識することで、失礼なく、そして心に残るやり取りができるようになります。
ビジネスメールでも使えるお礼の表現

ビジネスシーンにおいて、お中元やお歳暮を受け取った際には、形式に沿った丁寧なお礼の対応が求められます。近年では手紙ではなくメールでお礼を伝えるケースも増えていますが、ビジネスメールであっても礼儀や言葉遣いには十分配慮する必要があります。
まず、件名には相手が一目で内容を把握できるような言葉を使いましょう。たとえば「お中元御礼」「お歳暮の御礼申し上げます」などが適切です。これにより、ビジネスメールとしての整った印象を与えることができます。
本文では、冒頭の挨拶から丁寧に始めるのが基本です。「拝啓」などの頭語は使わず、「平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます」といった、ビジネスメールらしい定型的な表現を使うと良いでしょう。その後、贈り物をいただいたことへの感謝を明確に伝えます。
具体的な表現としては、以下のような文が役立ちます。
- 「このたびはご丁寧なお中元の品をお贈りいただき、誠にありがとうございました」
- 「社員一同でありがたく頂戴し、皆で美味しくいただきました」
- 「貴社のお心遣いに深く感謝申し上げます」
感謝の表現に加え、今後の関係性にも言及することで、ビジネスの文脈として自然な流れになります。例えば、「今後とも変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます」といった言い回しが好まれます。
メールの締めくくりには、季節に応じた気遣いの一言を添えるとより印象が良くなります。「厳しい暑さが続いておりますが、どうぞご自愛くださいませ」や「年末に向けご多忙のことと存じますが、皆様のご健康をお祈り申し上げます」といったフレーズがよく使われます。
なお、メールという形式上、あまり長文になりすぎないように注意しましょう。簡潔でありながらも、要点が明確に伝わる文章を心がけることが大切です。また、社外の相手に対しては、絵文字や口語表現は避け、あくまでビジネス文書としてのトーンを保つようにしましょう。
このように、ビジネスメールでも適切な構成と言葉選びを意識すれば、しっかりと感謝の気持ちを伝えることが可能です。形式よりも心がこもっているかどうかが、相手に伝わる鍵となります。
地元のギフトで感謝を形にする方法
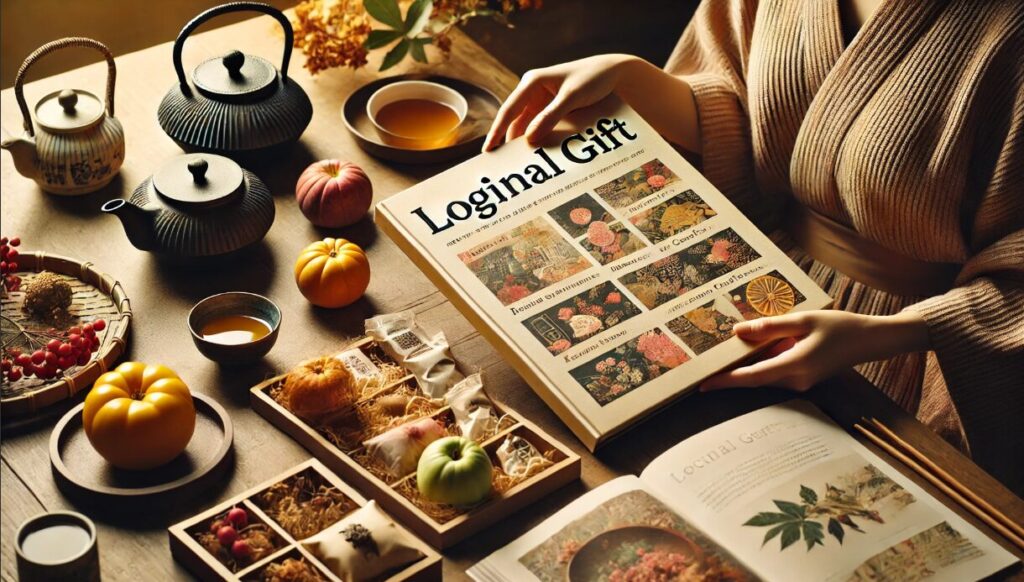
贈り物へのお礼を伝える手段は手紙やメールだけに限りません。「地元のギフト」を活用することで、感謝の気持ちを“形あるもの”として相手に届けることができる方法もあります。これは近年、オリジナリティや地域への思いを重視する方々の間で注目を集めている贈答スタイルです。

「地元のギフト」とは、各地域の特産品や生産者のこだわりが詰まった品々をカタログ形式で贈ることができるサービスです。特徴的なのは、ただ商品を選ぶのではなく、贈り主の出身地やゆかりのある土地の産品を贈ることができる点にあります。これにより、物だけでなく「想い」も同時に届けることが可能になります。
たとえば、自分の故郷が長野県であれば、「長野のりんご」「信州味噌」など、その土地ならではの品を贈ることができます。これにより、「あなたのことを思いながら選びました」というメッセージ性が自然と込められます。受け取る側にとっても、「普通のカタログギフトよりも印象に残った」という声が多く寄せられています。

また、地元のギフトには生産者のストーリーが添えられている場合が多く、「どうやって作られているのか」「どんな想いがこめられているのか」といった情報も伝えることができます。これによって、贈り物としての価値が単なる物理的なモノ以上の意味を持ち、より強い印象を残せます。
もちろん、すべてのケースで地元のギフトが適しているわけではありません。例えば、相手の好みがまったくわからない場合や、企業間のフォーマルなやり取りでは、ややパーソナルすぎると感じられることもあるでしょう。そうした場合は、汎用的なカタログギフトや定番品の方が適していることもあります。
それでも、感謝の気持ちを「より自分らしく」「記憶に残る形で」届けたいという場面では、地元のギフトは非常に効果的です。使い方次第で、単なる贈り物を「心を込めた特別なもの」に変えることができる点が、何よりの魅力といえるでしょう。
このように、文章では伝えきれない思いを込めてお礼を表現したい場合、「地元のギフト」という選択肢を検討してみる価値は十分にあります。感謝をカタチにし、相手の心にしっかりと届く贈り物を選びたい方には特におすすめです。
カジュアルなお礼状にも使える文例集

お中元やお歳暮のお礼状というと、格式ばった書き方をイメージする方が多いかもしれませんが、親しい間柄やカジュアルな関係性であれば、少しくだけた表現を取り入れても問題ありません。むしろ、相手との関係性によっては、堅苦しくない文体の方が、かえって気持ちが伝わりやすくなることもあります。
例えば、親しい友人や職場の同僚、昔から交流のある近所の方などに対しては、手紙というより“ちょっと丁寧なメッセージ”のような雰囲気で構成すると自然です。以下に、カジュアルなお礼状として使える文例をいくつか紹介します。
文例①(友人向け)
〇〇さん
暑さが続いてるけど、元気にしてますか?
このたびは美味しいお中元をありがとう!果物、大好きなのでとても嬉しかったよ。
家族でさっそくいただきました。甘くてジューシーで、夏を満喫できました。
いつも気にかけてくれて本当にありがとう。
これからも暑さが続くと思うけど、体に気をつけてね!
文例②(親戚向け)
〇〇叔母さんへ
こんにちは。先日は立派なお歳暮をいただき、ありがとうございました。
ローストビーフ、とっても美味しくて家族みんなで感動しながらいただきました!
年末の忙しい時期に、あたたかいお心遣いを本当に嬉しく思っています。
風邪など引かれませんよう、ご自愛ください。
文例③(知人向け)
〇〇様
こんにちは。このたびは素敵なお中元をお贈りいただき、ありがとうございます。
ジュースの詰め合わせ、とても美味しくて家族みんなで楽しませていただきました。
さわやかな夏の味で、元気が出ました。お心遣いに心から感謝いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
こうして見ると、書き方に少し差があることがわかります。カジュアルな文例では、格式ばった語彙を使わず、「ありがとう」「嬉しかった」「ごちそうさまでした」といった親しみのある表現が中心になります。また、エピソードを一言添えるだけで、ぐっと温かみのあるお礼状になります。
ただし、どれだけ親しい相手でも、極端にくだけた言葉遣いや絵文字、口語表現(例:「マジでうまかった」「ヤバかった」など)は避けましょう。手紙にはやはり“改まった印象”が求められるため、あくまで「丁寧さの中に親しみを感じさせる」バランスを意識するのがポイントです。
地元のギフトの特徴とおすすめポイント

贈り物に「地元のギフト」を選ぶ方が増えていますが、これはただのトレンドではなく、贈る側・受け取る側双方にとって多くのメリットがある新しいギフトの形です。ここでは、地元のギフトの具体的な特徴と、そのおすすめポイントについて詳しく解説します。
まず地元のギフトとは、贈る人の出身地や思い出の地域など、“土地に縁のある産品”を選んで贈ることができるカタログギフトサービスです。一般的なカタログギフトとは異なり、地域特産の食材や工芸品など、全国津々浦々の“地元の逸品”が一冊に集められており、「選ぶ楽しさ」も「贈る楽しさ」も味わえるのが特徴です。
具体的な魅力をいくつか挙げてみましょう。
1. 特別感がある
地元のギフトは、贈る人の「個性」や「ストーリー」が自然と伝わります。たとえば、「私の地元、山形のさくらんぼをお楽しみください」といったひと言を添えることで、贈り物が単なる物ではなく“思い出”や“つながり”として印象に残ります。
2. 選ぶ自由がある
受け取った相手は、数あるラインナップの中から自分の好みや必要に応じて好きな商品を選ぶことができます。食品・日用品・調味料などジャンルも幅広く、カタログ内の商品にはすべて生産者の紹介や背景エピソードが記載されており、「どんな想いで作られているのか」を知ることができるのも特徴です。
3. 社会的意義がある
地域の小規模な生産者を応援する意味でも、地元のギフトは社会的に価値のある選択です。復興支援や地産地消といったテーマにも貢献でき、“贈ることで誰かの力になれる”という充実感が得られる点も、多くの人に選ばれている理由の一つです。
4. 贈る相手を選ばない
フォーマルにもカジュアルにも対応できるのが強みです。結婚祝い、出産祝い、母の日・父の日、季節のご挨拶(お歳暮・お中元)など、幅広い用途で使えるため、「何を贈ればいいかわからない」と悩んだときの強い味方になります。
このように、地元のギフトは「贈る人の想い」と「地域の魅力」が詰まった、これまでになかったギフトスタイルです。どこか画一的になりがちなギフト文化の中で、“らしさ”や“背景”を伝えられる点が、最大の魅力といえるでしょう。
感謝やお祝いの気持ちを、モノだけでなくストーリーと一緒に届けたい方には、ぜひおすすめしたいギフトの選択肢です。


お歳暮お中元お礼状例文:個人向けのマナーと書き方まとめ
- お礼状は品物が届いてから3日以内が理想
- 受け取り報告も兼ねて早めの連絡が望ましい
- お礼が遅れた場合は一言お詫びを添えると丁寧
- 親戚には形式よりも親しみやすさを重視する
- 柔らかい言葉で感謝を伝えると印象が良い
- 略式すぎる表現や絵文字は避けるべき
- 食べ物への感謝は具体的な感想を書くと伝わりやすい
- 好みに合わない品でも丁寧な言葉で感謝を表す
- 果物のお礼状には季節感や味の感想を添えるとよい
- お礼状のテンプレートを活用すると文章作成が簡単
- 時候の挨拶を使うと季節感が出て礼儀も整う
- 親しい相手には少し砕けた言葉でも気持ちが伝わる
- ビジネスメールでは簡潔で丁寧な言葉選びが大切
- 地元のギフトは個性と地域性を伝える手段となる
- ギフトの背景やストーリーを添えると特別感が増す
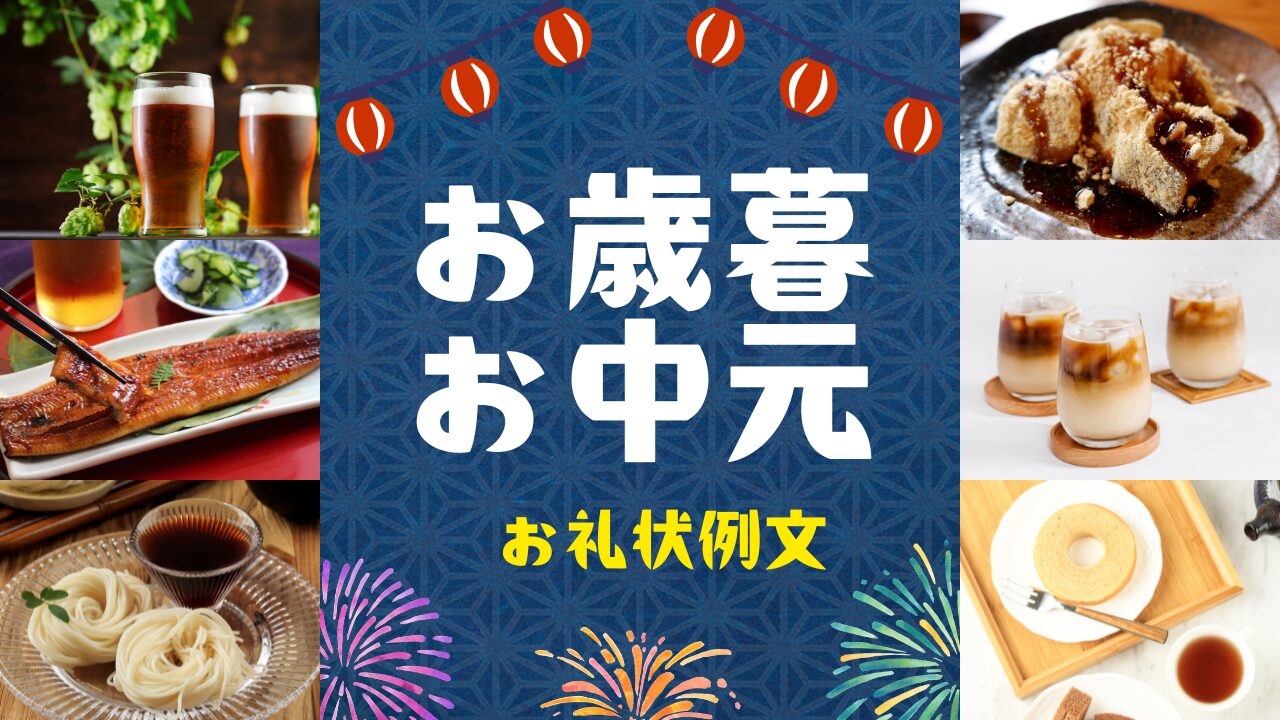

コメント