出産祝いをいただいたら、お返しの準備を考える必要がある。しかし、初めての出産となると、「お返しの時期は早いほうがいいのか」「親族への金額はどのくらいが適切なのか」など、マナーについて迷うことも多い。
特に、出産祝いのお返しをいつまでに贈ればよいのかは、多くの人が気にするポイントだ。一般的な目安や適切な対応を知ることで、相手に失礼のない形で感謝を伝えることができる。本記事では、出産祝いのお返しの基本マナーや金額の目安をわかりやすく解説する。
- 出産祝いのお返しを贈る適切な時期とその理由
- お返しが遅れた場合の対処法とマナー
- 親族や職場へのお返しの相場と金額の目安
- 出産内祝いの熨斗や贈り方のマナー
出産祝いのお返しはいつまでに贈る?適切な時期とマナー
- 出産祝いのお返しの時期は早いほうがいい?
- お返しがないのはマナー違反?注意点を解説
- 職場の出産祝いのお返しはいつがベスト?
- 出産祝いのお返しの相場|親族への金額目安
- 出産内祝いのマナー|贈る時期や熨斗の選び方
- 出産祝いのお返しランキング|人気ギフトを紹介
出産祝いのお返しの時期は早いほうがいい?

出産祝いのお返しは早めに贈ることが理想的です。一般的な目安として、生後1ヶ月頃のお宮参りの時期までに贈るのがよいとされています。しかし、産後は赤ちゃんのお世話や母体の回復に時間がかかることも多く、すぐに準備ができるとは限りません。そのため、遅くとも2ヶ月以内には贈るように心がけることが望ましいです。
早めにお返しを贈るべき理由として、相手に対する感謝の気持ちを迅速に伝えることが挙げられます。出産祝いは、贈り手が「赤ちゃんの誕生を祝いたい」という気持ちを込めて贈ってくれたものです。そのお礼を長期間放置してしまうと、感謝の気持ちが十分に伝わらなかったり、相手に「忘れられたのではないか」という印象を与えてしまうこともあります。
例えば、祖父母や親戚、友人などが出産祝いを贈った場合、遅くなってしまうと「こちらから催促しないといけないのかな」と気を遣わせる可能性があります。また、職場関係者へのお返しが遅れると、復帰後の人間関係にも影響することがあります。特に、上司や取引先など目上の方からの出産祝いに対しては、マナーを意識して早めに対応することが重要です。
ただし、産後の体調によってはすぐに準備できない場合もあります。そのようなときは、まずは電話やメールで「お祝いをいただいたことへの感謝」を伝えるだけでも、相手に誠意が伝わります。その後、できる限り早くお返しの手配を進めるようにしましょう。また、事前に出産内祝いをリストアップし、出産前に準備を進めておくと、産後の負担を減らすことができます。
いずれにしても、出産祝いのお返しは早い方が相手への印象もよく、マナーとしても適切です。とはいえ、無理をしてまで早く贈る必要はありません。相手への気遣いを忘れず、自分の体調や育児の状況を考慮しながら、可能な範囲でスムーズに準備を進めることが大切です。
お返しがないのはマナー違反?注意点を解説
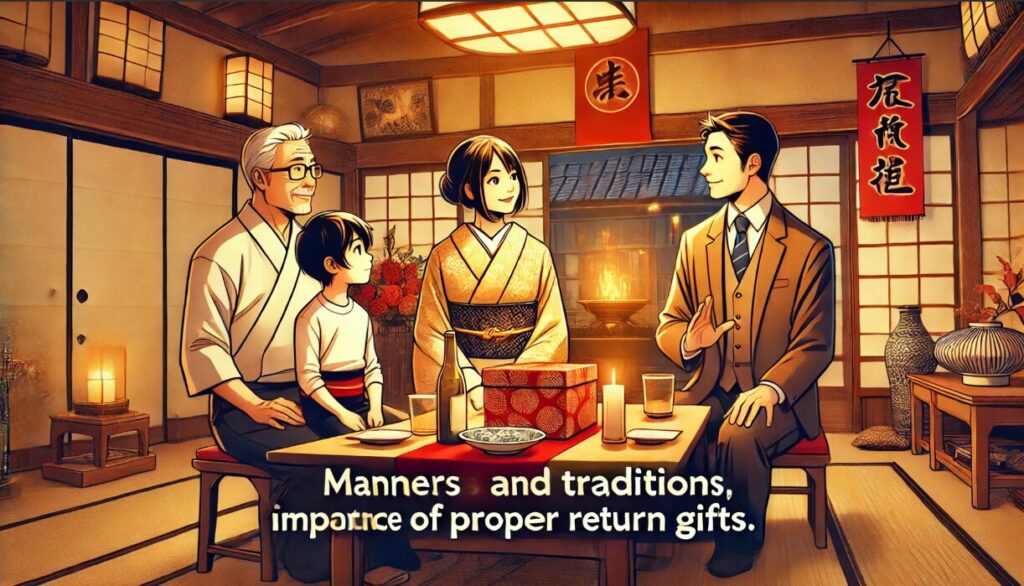
出産祝いをいただいたにもかかわらず、お返しをしないのは基本的にマナー違反とされています。お祝いは、相手が赤ちゃんの誕生を祝福し、気持ちを込めて贈ってくれたものです。その気持ちに対して何の反応も示さないと、相手に失礼にあたる可能性があります。特に、目上の方や親戚、職場関係者からの出産祝いは、しっかりとお礼を伝え、お返しをするのが社会的なマナーです。
一方で、「お返しはいらないからね」と言われることもあります。このような場合でも、感謝の気持ちを示すために、何かしらの形でお礼をすることをおすすめします。例えば、高額な内祝いではなく、気持ち程度の品物を贈ったり、赤ちゃんの写真入りのメッセージカードを添えるだけでも、相手は喜んでくれるでしょう。
また、お祝いをもらってからお返しの時期が遅れすぎると、相手に「忘れられたのでは?」という印象を与えてしまいます。たとえ遅れてしまった場合でも、必ずお詫びの言葉を添えて贈ることが大切です。例えば、「産後の慌ただしさでお礼が遅くなってしまい申し訳ありません」など、一言添えるだけで、相手も安心し、気持ちよく受け取ってくれるでしょう。
お返しをしないことで相手に誤解を与えたり、今後の関係性に影響を及ぼす可能性があるため、できる限り内祝いを用意することが望ましいです。ただし、親や兄弟などごく親しい間柄では、お返しの必要がない場合もあります。その場合でも、電話や直接会った際にしっかりとお礼を伝えることを忘れないようにしましょう。
特に気をつけたいのが、弔事と重なった場合です。相手が喪中の場合、すぐにお祝いのお返しをするのは避け、四十九日を過ぎた頃を目安に贈るようにするのがマナーです。その際は、「お祝いのお礼」として贈るのではなく、「感謝の気持ち」として相手の負担にならない形で贈ることをおすすめします。
出産祝いのお返しは、相手との関係を大切にするための大事なマナーです。相手の立場や状況を考えながら、心を込めてお返しをすることが、円滑な人間関係を築くことにつながるでしょう。
職場の出産祝いのお返しはいつがベスト?

職場の同僚や上司、部下などから出産祝いをいただいた場合、お返しの時期は特に注意が必要です。一般的なマナーとしては、出産後1ヶ月を目安に贈るのがよいとされています。ただし、職場への復帰前に贈るのが理想的であり、遅くとも2ヶ月以内には用意しましょう。
職場の人々は、産後の状況を理解している場合が多いため、多少遅れてしまっても問題にはなりません。しかし、育休からの復帰後に渡すのは避けたほうがよいでしょう。職場復帰後にお返しをすると、「もう過ぎたことなのに今さら?」という印象を与えてしまう可能性があるためです。そのため、復帰前にオンライン注文などを活用して早めに準備するのがおすすめです。
また、職場では個別にお祝いをもらうこともあれば、部署単位やグループでまとめて贈られることもあります。その場合は、個別にお返しを用意するよりも、みんなで分けられる菓子折りなどを選ぶのが一般的です。例えば、日持ちのする焼き菓子や、小分けになったお菓子の詰め合わせを選ぶと、受け取る側も気軽に楽しめます。
一方、個人的に高額な出産祝いをいただいた場合は、その方に対して個別にお返しをすることが望ましいです。その際、いただいた金額の「半返し」または「3分の1返し」を目安に、相手の好みに合うギフトを選ぶとよいでしょう。
職場での人間関係を円滑に保つためにも、出産祝いのお返しは適切な時期に、相手に負担をかけない形で贈ることが大切です。出産後の忙しい時期でも、オンラインストアを活用すればスムーズに準備ができるため、事前にリストアップしておくとよいでしょう。
出産祝いのお返しの相場|親族への金額目安
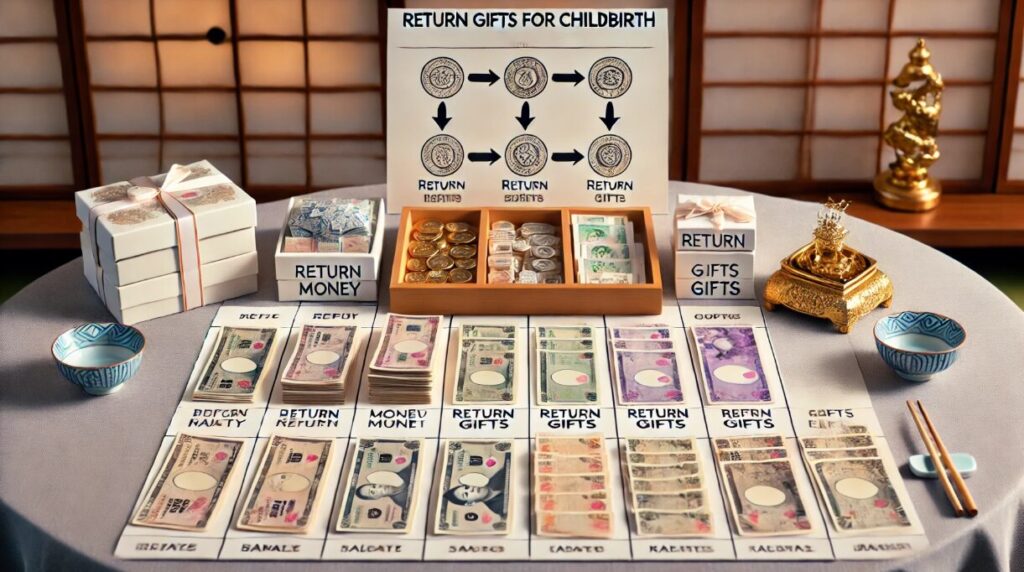
出産祝いのお返しの相場は、いただいたお祝いの金額によって変わります。一般的には「半返し」が基本とされ、いただいた金額の約2分の1を目安にお返しをするのが適切です。ただし、親族の場合は関係性によって相場が異なるため、単純に半額で計算するのではなく、状況に応じた対応が求められます。
例えば、祖父母からの出産祝いは比較的高額になることが多く、5万円から10万円、場合によってはそれ以上をいただくケースもあります。このような場合、半額を返すとなると負担が大きくなってしまうため、3分の1程度のお返しが一般的です。つまり、10万円のお祝いをいただいた場合、3万円前後のお返しを選ぶとよいでしょう。また、祖父母の場合は、「お返しは不要だから、その分赤ちゃんのために使ってほしい」と言われることもあります。その場合でも、何かしらの記念品や赤ちゃんの写真入りのギフトを贈ることで、感謝の気持ちをしっかり伝えることができます。
次に、叔父や叔母、兄弟姉妹からの出産祝いについて考えてみましょう。この場合、相場は1万円から3万円程度が多いため、半返しの5,000円〜1万5,000円程度のお返しを用意するのが適切です。特に、兄弟姉妹には「お互いさま」の考え方があるため、過去に自分が出産祝いを贈ったことがある場合は、そのときの金額を参考にしてお返しをするとよいでしょう。
また、いとこや遠い親戚からのお祝いは、3,000円〜1万円程度の場合が多く、半額または3分の1の金額のお返しをするのが無難です。相手との関係性を考慮しつつ、適切なギフトを選びましょう。
親族へのお返しは、お礼状や赤ちゃんの写真を添えることで、より気持ちが伝わります。単なる金額のやり取りではなく、感謝の気持ちを表すことが大切です。そのため、相手の好みに合わせたギフトや記念に残る品を選ぶことを意識すると、喜ばれる内祝いになります。
出産内祝いのマナー|贈る時期や熨斗の選び方

出産内祝いを贈る際には、適切な時期や熨斗(のし)のマナーを守ることが重要です。一般的に、出産内祝いは赤ちゃんの生後1ヶ月頃、お宮参りのタイミングで贈るのが目安とされています。ただし、産後の母体の回復状況や育児の負担を考慮し、遅くとも2ヶ月以内には贈るようにしましょう。
また、出産祝いを後からいただくこともあります。その場合、お祝いを受け取ってから1ヶ月以内にお返しをするのがマナーです。万が一、内祝いが遅くなってしまった場合は、お詫びの言葉を添えつつ、できるだけ早く対応することが大切です。
熨斗の選び方についても注意が必要です。出産内祝いでは、「紅白の蝶結び(花結び)」の水引を使用するのが一般的です。この結び方は、何度でも結び直せることから「何度あっても嬉しいお祝いごと」に適しているとされています。表書きには「内祝」または「出産内祝」と記載し、赤ちゃんの名前を入れます。ふりがなをつけると、相手にとってもわかりやすく親切です。
また、相手が喪中の場合、出産内祝いを贈るタイミングに配慮することが求められます。忌中(四十九日が終わるまで)の間は贈らないのが一般的であり、忌明け後に「御礼」として贈るとよいでしょう。その際は、お祝いの要素を抑え、落ち着いた包装や品物を選ぶことが適切です。
このように、出産内祝いはただ贈るだけでなく、時期や熨斗のマナーを守ることで、より丁寧な印象を与えることができます。相手に喜んでもらえるよう、細かな気配りを忘れずに準備を進めましょう。
こちらの記事もオススメです(^^)/

出産祝いのお返しランキング|人気ギフトを紹介

出産祝いのお返しとして、相手に喜ばれるギフトを選ぶことはとても重要です。多くの人に選ばれている人気のギフトをランキング形式で紹介します。
1位:カタログギフト
カタログギフトは、相手に好きなものを選んでもらえるため、非常に人気があります。特に、食べ物や日用品、ブランドアイテムなど、幅広い選択肢があるものを選ぶと、どんな方にも喜ばれやすいです。また、遠方の方にも贈りやすく、相手の好みに左右されないのが魅力です。
2位:スイーツや高級菓子
出産内祝いでは、焼き菓子や和菓子、チョコレートなどのスイーツが人気です。特に、個包装になっているものや、賞味期限が長めのものは、受け取った側が好きなタイミングで楽しめるため喜ばれます。
3位:コーヒー・紅茶セット
コーヒーや紅茶のギフトセットも、幅広い年代の方に喜ばれる定番アイテムです。特に、ブランドのものやオーガニック素材のものは人気が高く、リラックスできる時間を提供できる贈り物になります。
4位:高級タオルセット
実用性のあるギフトとして、高級タオルも根強い人気を誇ります。今治タオルなどの上質なタオルは、使い心地がよく、長く愛用してもらえるため、お祝いのお返しにぴったりです。
5位:お米ギフト
赤ちゃんの体重と同じ重さのお米を贈る「体重米」や、高級ブランド米の詰め合わせも人気があります。食べ物ギフトの中でも、お米は好みを問わず実用性が高いため、幅広い方に贈りやすいです。
6位:【地元のギフト】
最近注目されているのが「地元のギフト」です。各地域の特産品や名産品を贈ることで、オリジナリティのあるお返しができます。例えば、北海道なら乳製品や海産物、京都なら和菓子やお茶など、地域ごとの魅力を活かしたギフトは、相手にも新鮮な喜びを提供できます。

このように、出産祝いのお返しは、相手の好みやライフスタイルを考慮しながら選ぶことが大切です。カタログギフトやスイーツなどの定番ギフトから、地元の特産品を活かしたものまで、多様な選択肢があります。相手に喜ばれるギフトを選んで、感謝の気持ちをしっかり伝えましょう。
出産祝いのお返しはいつまで?【地元のギフト】がセンスよくておすすめ
- 【地元のギフト】とは?魅力とメリットを解説
- 出産内祝いにセンスのいいギフトを選ぶコツ
- 結婚内祝いはいつまでに返す?出産内祝いとの違い
- 出産祝いのお返しを贈るときに注意すべきマナー
- まとめ|感謝の気持ちを伝えるためのポイント
【地元のギフト】とは?魅力とメリットを解説

【地元のギフト】とは、各地域の特産品や名産品を活かした贈り物のことを指します。最近では、全国各地の美味しい食材や工芸品を手軽に購入できるサービスも増え、お取り寄せ感覚で楽しめるギフトとして人気を集めています。出産内祝いとしても選ばれることが多く、贈る相手に特別な価値を提供できる点が大きな魅力です。
【地元のギフト】の最大のメリットは、オリジナリティがあることです。一般的な内祝いのギフトは、カタログギフトやスイーツ、タオルセットなどが定番ですが、それらはどこでも手に入るため、ありきたりな印象を与えてしまうこともあります。一方で、地元の特産品を選ぶことで、「この地域ならではの贈り物」という特別感を演出できます。例えば、北海道なら新鮮な海産物や乳製品、京都なら伝統的な和菓子やお茶など、地域ごとの魅力を活かしたギフトは受け取る側にも新鮮な喜びを提供できます。

また、地元のギフトは品質が高いこともメリットの一つです。地域の特産品として長年愛されてきたものは、素材や製法にこだわりがあり、味や使い心地の良さが保証されています。特に、食べ物系のギフトは贈る相手の好みに左右されにくく、幅広い層に喜ばれやすいのが特徴です。
さらに、地元のギフトを選ぶことで、その地域の経済を応援することにもつながります。特産品を購入することで地元の生産者を支援し、地域活性化の一助となることは、贈る側にとっても意義のある選択肢となります。
ただし、地元のギフトを選ぶ際には、相手の好みやアレルギーの有無を考慮することが大切です。例えば、日本酒やワインなどのアルコール類を贈る場合は、相手が飲酒するかどうかを確認する必要があります。また、生鮮食品は賞味期限が短いものも多いため、配送のタイミングや相手が受け取りやすい日程を考慮することも重要です。

このように、【地元のギフト】は、特別感や品質の高さを重視したい方にぴったりの贈り物です。地域ごとの魅力を活かしたギフトを選ぶことで、相手に喜ばれるだけでなく、自分自身の出身地や住んでいる地域の良さを再発見する機会にもなります。
出産内祝いにセンスのいいギフトを選ぶコツ

出産内祝いを選ぶ際、ただ人気の商品を選ぶだけではなく、「センスのいいギフト」を意識することで、より喜ばれる贈り物になります。センスの良いギフトとは、受け取った相手が「特別感がある」「自分のことを考えて選んでくれた」と感じられるものです。そのためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
まず、相手のライフスタイルや好みを考慮することが重要です。例えば、甘いものが好きな方には高級スイーツを選ぶのが適していますが、甘いものが苦手な方にはコーヒーや紅茶、食器セットなどの実用的なものを選ぶとよいでしょう。また、健康志向の方にはオーガニック食品やヘルシーなお菓子を選ぶと、より満足度の高いギフトになります。
次に、パッケージデザインにもこだわることが大切です。どんなに良い商品でも、見た目がシンプルすぎたり、チープな印象を与えてしまうと、センスの良さが半減してしまいます。最近では、高級感のあるギフトボックスや、和モダンなデザインの包装が人気を集めています。例えば、シンプルながらも洗練されたデザインの和菓子や、上品なラッピングが施されたコーヒーギフトなどは、特別感があり、相手に好印象を与えます。
さらに、オーダーメイドや名入れギフトを選ぶのもおすすめです。例えば、赤ちゃんの名前が入ったフォトフレームや、オリジナルのメッセージカード付きのお菓子セットなどは、もらった側にとっても記念に残るギフトになります。ただし、名入れギフトは制作に時間がかかることがあるため、早めに注文するようにしましょう。
最後に、ギフトの内容だけでなく、「渡し方」もセンスの良さを左右します。特に、手渡しする場合は、きちんとした手提げ袋に入れたり、相手に直接感謝の気持ちを伝えることが大切です。配送で贈る場合でも、手書きのメッセージカードを添えることで、より温かみのある内祝いになります。
このように、センスの良い出産内祝いを選ぶには、相手の好みやライフスタイルを考え、パッケージやデザイン、渡し方まで工夫することが大切です。特別感のあるギフトを贈ることで、より心のこもった感謝の気持ちを伝えられるでしょう。
こちらの記事もオススメです(^^)/


結婚内祝いはいつまでに返す?出産内祝いとの違い
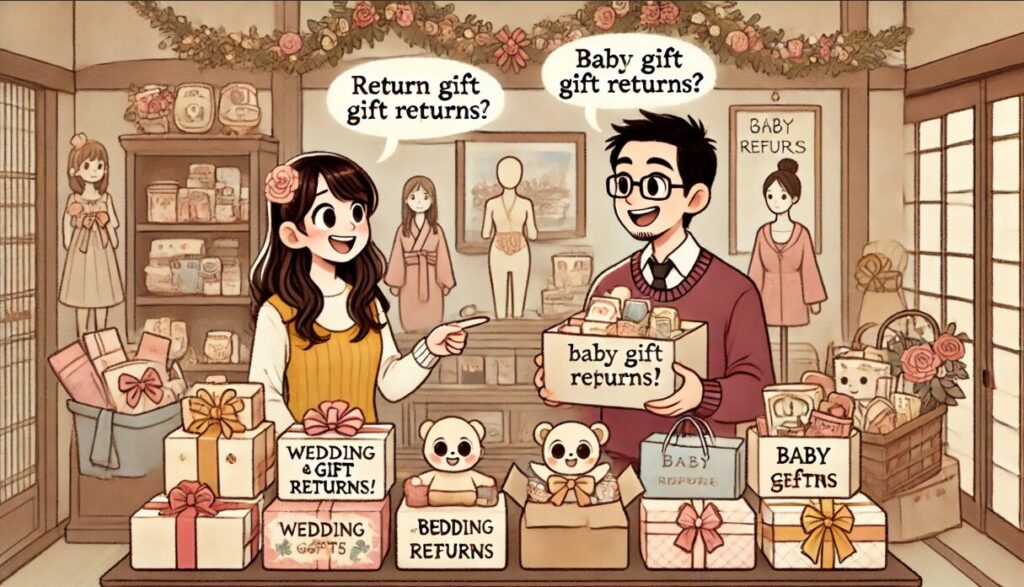
結婚内祝いと出産内祝いはどちらも「お祝いのお返し」という点では共通していますが、贈るタイミングや選ぶギフトの種類に違いがあります。それぞれのマナーを理解して、適切に対応することが大切です。
結婚内祝いは、結婚式に参列しなかった方からお祝いをいただいた場合に贈るお返しのことを指します。贈るタイミングとしては、結婚式の1ヶ月後から2ヶ月以内が目安です。遅くなりすぎると、お祝いをいただいた方に対して失礼にあたるため、できるだけ早めに準備しましょう。また、結婚式を挙げない場合でも、結婚祝いをもらった際には、同じ時期を目安にお返しをするのがマナーとされています。
一方、出産内祝いは、赤ちゃんの誕生を祝っていただいたお祝いに対するお返しのことを指します。基本的に、赤ちゃんが生後1ヶ月頃のお宮参りの時期に贈るのが一般的です。産後の体調や育児の状況によっては遅れることもありますが、遅くとも2ヶ月以内には贈るようにしましょう。
また、ギフトの選び方にも違いがあります。結婚内祝いでは、ペアグラスや高級タオルセット、食器セットなど、夫婦で使える実用的なアイテムが人気です。一方、出産内祝いでは、お菓子やカタログギフト、名入れの記念品など、感謝の気持ちを込めたギフトが好まれます。
このように、結婚内祝いと出産内祝いは、それぞれ贈るタイミングやギフトの内容が異なります。どちらの場合も、相手の立場を考慮し、マナーを守った対応を心がけることが大切です。
出産祝いのお返しを贈るときに注意すべきマナー

出産祝いのお返し(出産内祝い)を贈る際には、いくつかのマナーを守ることが大切です。相手への感謝の気持ちをしっかりと伝え、失礼のない形でお返しをすることで、今後の関係を良好に保つことができます。特に注意すべきポイントを具体的に解説します。
1. お返しを贈る時期を守る
出産内祝いを贈る一般的なタイミングは、赤ちゃんの生後1ヶ月頃、お宮参りの時期とされています。ただし、産後の体調や育児の状況によっては、すぐに対応するのが難しい場合もあります。そのようなときは、遅くとも生後2ヶ月以内に贈るようにしましょう。
また、出産祝いを後からいただくこともあります。その場合、いただいてから1ヶ月以内を目安にお返しをするのがマナーです。万が一、内祝いが遅くなってしまった場合は、お詫びの一言を添えることで相手に誠意が伝わります。
2. お祝いの金額に応じたお返しを選ぶ
出産祝いのお返しの相場は、「半返し」が基本です。つまり、いただいた金額の半額程度の品を選ぶのが一般的ですが、親族や目上の方から高額なお祝いをいただいた場合は、3分の1程度にとどめるのが適切です。逆に、少額のお祝いに対しては、相手に気を遣わせないよう、ちょうど良い価格帯の品を選ぶことが大切です。
例えば、5,000円のお祝いをいただいた場合は、2,500円程度のお返しを、10,000円のお祝いなら5,000円程度を目安にすると良いでしょう。ただし、地域の習慣や家庭ごとのルールもあるため、事前に確認しておくと安心です。
3. 熨斗(のし)を正しくつける
出産内祝いには、必ず「紅白の蝶結び」の熨斗をつけます。この蝶結びは、「何度あっても嬉しいお祝いごと」に適しており、出産内祝いには最適です。熨斗の表書きには「内祝」または「出産内祝」と記載し、贈り主として赤ちゃんの名前を記入します。ふりがなをつけると、相手が読みやすく、より親切な印象を与えます。
また、相手が喪中の場合は注意が必要です。通常のお祝いのタイミングで贈るのは避け、四十九日が過ぎてから「御礼」の形で贈るようにしましょう。その際は、熨斗を控えめなデザインにするなど、配慮を忘れないことが大切です。
4. 相手のライフスタイルに合ったギフトを選ぶ
せっかくのお返しも、相手にとって使いづらいものだと喜ばれにくくなります。例えば、一人暮らしの方に大量の食品を贈ると食べきれないことがありますし、アルコール類を飲まない方にワインや日本酒を贈るのは適切ではありません。
人気の出産内祝いには、スイーツやコーヒー、タオルなど実用性のあるアイテムが含まれますが、できるだけ相手の好みや生活スタイルに合ったものを選ぶと、より喜んでもらえます。最近では、カタログギフトや【地元のギフト】のように、相手が自由に選べる形式のものも人気が高まっています。
5. メッセージカードや手紙を添える
お返しの品を贈るだけでなく、感謝の気持ちを伝えるためにメッセージカードや手紙を添えると、より丁寧な印象を与えます。簡単なもので構いませんが、「お祝いをいただいたことへの感謝」「赤ちゃんが元気に育っていること」「今後も変わらぬお付き合いをお願いしたい気持ち」などを伝えると良いでしょう。
例えば、「この度は温かいお祝いをいただき、ありがとうございました。おかげさまで赤ちゃんも元気に育っています。ささやかではありますが、お礼の気持ちとしてお贈りいたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします。」といったメッセージが適切です。
以上のように、出産内祝いを贈る際には、時期・金額・熨斗のマナー・ギフトの選び方・メッセージの添え方に気をつけることで、相手に喜ばれるお返しができます。感謝の気持ちを伝えつつ、丁寧な対応を心がけましょう。
まとめ|感謝の気持ちを伝えるためのポイント

出産祝いのお返しは、単に形式的なものではなく、相手に感謝の気持ちを伝える大切な機会です。そのため、適切な時期に、マナーを守りながら贈ることが重要です。ここでは、感謝の気持ちをしっかりと伝えるためのポイントをまとめます。
1. 適切な時期にお返しを贈る
出産内祝いは、生後1ヶ月のお宮参りの頃を目安に贈るのが一般的です。ただし、産後の状況によって準備が難しい場合は、無理をせず、遅くとも2ヶ月以内にはお返しを済ませるようにしましょう。また、出産祝いを後からいただいた場合は、1ヶ月以内を目安にお返しをすることで、相手に失礼のない対応ができます。
2. 相手に合ったギフトを選ぶ
ギフトは、相手のライフスタイルや好みに合ったものを選ぶことが大切です。食品や日用品など、誰にでも喜ばれやすいものを選ぶのも良いですが、最近ではカタログギフトや【地元のギフト】など、相手が自由に選べる形式のものも人気があります。
3. 熨斗や包装のマナーを守る
出産内祝いには「紅白の蝶結び」の熨斗をつけ、赤ちゃんの名前を記入するのが基本です。相手が喪中の場合は、タイミングを配慮し、落ち着いたデザインの包装を選ぶと良いでしょう。
4. メッセージを添えて心を込める
品物を贈るだけでなく、メッセージカードや手紙を添えることで、より温かみのあるお返しになります。簡単な文章でも構わないので、感謝の気持ちをしっかりと伝えることが大切です。
5. 相手の負担にならないよう配慮する
お返しの金額は「半返し」が基本ですが、目上の方には3分の1程度の品を選ぶことが適切です。また、高価すぎる品物は相手に負担を感じさせてしまうことがあるため、適度な価格帯のものを選ぶようにしましょう。
出産内祝いは、贈る側の気遣いが相手に伝わる大切な機会です。感謝の気持ちを形にし、相手が気持ちよく受け取れるよう、マナーを守った対応を心がけましょう。
出産祝いのお返しはいつまでに贈るべき?適切な時期とマナー
- 出産祝いのお返しは、生後1ヶ月のお宮参りの時期を目安に贈る
- 遅くとも2ヶ月以内には贈るのが望ましい
- お返しが遅れる場合は、先に感謝の気持ちを伝えることが重要
- お祝いをもらったら、1ヶ月以内にお返しをするのが基本
- 産後の体調を考慮し、無理のない範囲で準備を進める
- 職場へのお返しは復帰前に贈るのがベスト
- お返しの相場は、いただいた金額の半額から3分の1程度
- 親族からの高額なお祝いには、記念品や感謝の品を添える
- 出産内祝いの熨斗は「紅白の蝶結び」を使用する
- カタログギフトや地元の特産品は、喜ばれやすい内祝いの選択肢
- お返しが不要と言われた場合も、何かしらの形で感謝を伝える
- 目上の方へのお返しは、特に丁寧な対応を心がける
- 喪中の方へは、忌明け後に「御礼」として贈る
- ギフトには手書きのメッセージカードを添えると好印象
- 相手のライフスタイルや好みに合った贈り物を選ぶことが大切
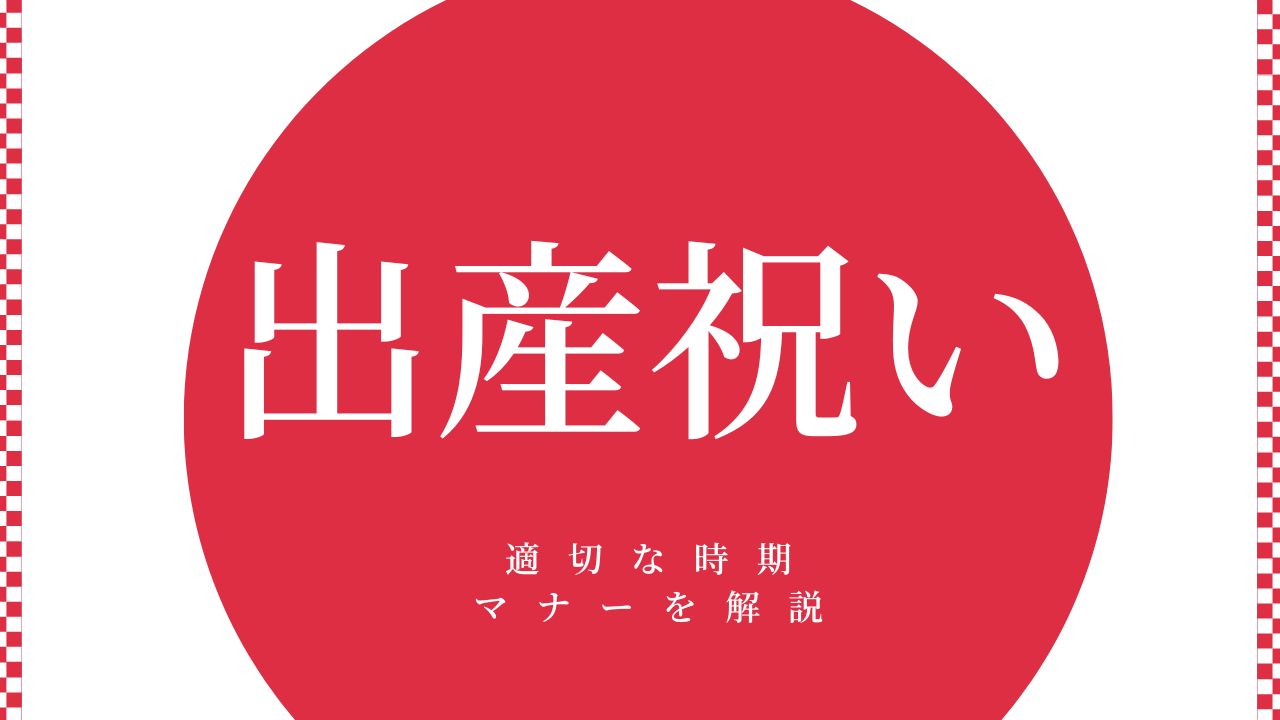


コメント